2023/09/20 第25回
ODA (政府開発援助official development assistance) は「北」の豊かな工業国が「南
」の貧しい農業国に融資する国際的な取りくみである。ODAといえども大部分の貸付金は
利子をつけて返済することになっている。たとえば年率5%で借りると14年後には元利合
わせて2倍を返済しなければならない。
貸付金で生産基盤を整え、製品を輸出して元利以上に外貨を稼がないと、借金地獄に陥
る。すでに、多くの南の国は貸付・援助の融資より返済が多くなっている〈図1〉。
これが援助といえるのか。ODAがもたらしたものは貧富の差の拡大、ひいては食料配分
の偏りの激化ではないか。ついに、「南」のメキシコは1982年に返済不可能を申したてた
が「北」はこれを許さない。ペソの切りさげによる輸出の促進、はては、麻薬生産を黙認
して、借金の返済をせまった。また、アフリカのチャド、ニジェールなどは食料が絶対的
に不足しているのに、借金返済のために、食料ではなく綿花などの換金作物の生産が強い
られている。
図1.「北」は「南」に毎年1030億ドルを貸付けているが、同時に
「南」は1495億ドルを返済している(S.George, 1992より作図)。
発展途上国から、援助以上を回収している援助国もどきが多すぎないか。真の援助は自
立できる援助をつうじて、やがて援助を不要とする援助ではないか。
【コラム2.3】 自立できる援助を
ベトナムの病院で現地の人は日本人にはにこやかに挨拶・対応してくる。理由がわかり
、誇らしく思った。
ODA の一環として日本政府が瀟洒な病院を建てた。最先端の機器類も設置した。使える
人が限られるのでこれらはやがて劣化していった。これでは意味ある援助にはならないと
日本の医者数名がボランティアで滞在し、現地の人たちを医者に育てた。今は、育った医
者が現地の人を医者に育てるというプラスの循環が確立している。心のこもったボランテ
ィア援助である。まさしく自立できる援助である。

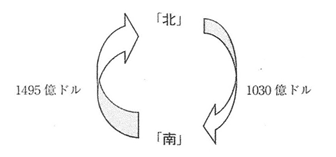
コメント